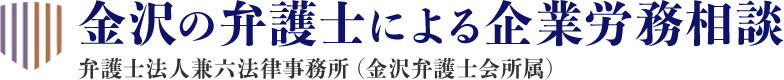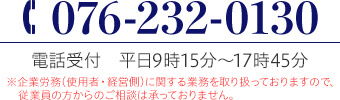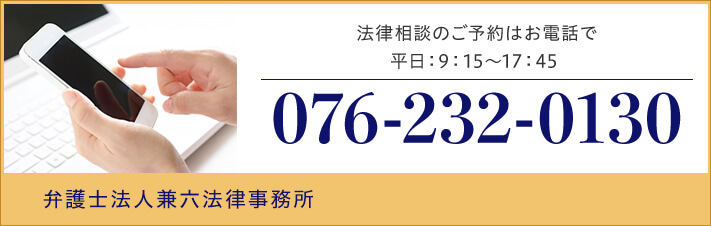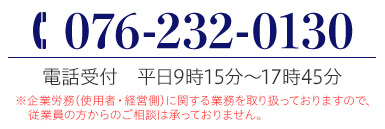従業員が会社の金銭を横領するという事件が時折報道されることがあります。今回は,社内で横領事件が起きた場合の適切な対応についてお話ししたいと思います。
1 よくある横領の手口
会社での横領とは,従業員などが,仕事で管理している会社の財産を自分のものにしてしまうということです。社内で金品を管理する業務を担当する社員が手を染めてしまう犯罪です。
少し前に「最も美しい横領犯」というキャッチコピーで話題になった映画がありましたが,作中では銀行員が払い戻しの書類を偽造して預金を引き出し,自分のものにしてしまう,という横領の手口でした。
その他,会社の集金担当が集金した現金を少なく報告し差額を着服する,経理担当が書類を偽造し架空の取引があったと偽って現金を引き出す,といった横領の手口がよくみられます。
2 まずは客観資料の収集
横領は重大な非違行為であり,社内への影響も大きいため,なによりもまずは事実関係の調査を徹底して行い,事実を確定させる必要があります。
会社が横領の事実を把握したといっても,それをもって従業員を処分するのであれば,合理的な根拠をもって説明できるものでなければなりません。
また,疑惑の状態で本人を追及してしまうと,事実を否認されたり,証拠隠滅が図られたりすることもありますので,まずは客観的な資料の収集から始めるべきでしょう。
収集する資料は,事案によりますが,口座の出入金記録,取引先の見積書・請求書,領収証,入出金伝票など,金銭の出入りを証明する資料を集めて,金銭の流れを調べるべきだと考えられます。
そこから,実際に出金された金額と出金されるべき金額を突き合わせて,使途不明金の有無・回数・金額などを確定させるべきです。
3 関係者の事情聴取
客観的に使途不明金が発生していることがわかったら,横領行為をしたとみられる従業員本人や関係者から事情を聴き取ります。
このとき,とくに従業員本人への事情聴取は,不正行為を認めさせて終わりにすることが多くなってしまいそうですが,それだけでは一体何をしたのかわかりません。
あくまで目的は事実の調査ですので,可能な限り具体的に事情を聴き出すことを目標としなければなりません。
聴取した内容は,いわゆる5W1H(誰が・何を・いつ・どこで・なぜ・どのように)がはっきりわかるように記録しておいてください。
本人が否定した場合でも,詳細に聴き取ることで,客観的な資料と照らし合わせやすくなりますから,不明な点を追加で説明してもらったり,矛盾点を洗い出すことで本人の弁明が信用できるかどうかを判断しやすくなったり,聴取した内容に関連する追加の資料を収集していくヒントにもなります。
なお,調査の後,処分を懲戒解雇とする場合は,従業員に対する影響が大きいため,どうしても実施できないような場合を除き,従業員に対して弁明の機会を与えなければ懲戒解雇は違法と判断される可能性が高いと考えられます。
口頭で事情を聴取することや,文書(始末書・顛末書など)で書いてもらうといったかたちでも,本人から事情を聴いて,弁解をそのまま記録しておくことが大切です。
4 自宅待機
横領が疑われる従業員が出勤してしまうと,客観的な資料の破棄や関係者との口裏合わせ等,横領の証拠が隠滅されてしまうおそれがあるのであれば,事実の調査を行う間は自宅待機命令(出勤停止措置)を発動することも考えられます。
この自宅待機命令(出勤停止措置)は,懲戒解雇相当の重い懲戒事由が疑われる場合に,事実関係の調査または処分内容を判断するまでの間,会社への出勤を禁止する業務命令です。
その従業員が保管しているために客観的な資料を収集すると本人にわかってしまうとか,社内の関係性からみて口裏合わせがされてしまいそうな場合には,自宅待機を命じるのも1つの手です。
5 処分の検討
事実関係を調査した結果,従業員が横領をしていたことが確定できれば,その従業員に対する処分を検討することになります。
最終的な処分内容は,行為態様,損害額,賠償額,その従業員の立場,過去の処分例とのバランスなどの要素を考慮して判断します。
こと横領は,それ自体社内の秩序を大きく乱す重大な非違行為ですから,横領した場合には,重い処分を下すことが可能だという判断に傾きます。実際にも,横領を理由とする懲戒解雇が争われた多くの裁判例で,懲戒解雇が有効だと判断されています。
逆に,客観的資料や関係者の供述といった証拠からみて,横領したとまでは確定できないケースなどであれば,解雇することまではできない可能性が高いと考えられます。
この場合は,業務上のミスなどとして厳重注意などの比較的軽い処分を課すか,処分しないという判断とすべきでしょう。
横領は犯罪行為にあたるため,悪質なケースでは,刑事告訴も選択肢に入ると思います。
この場合,その従業員に前科・前歴がついて社会生活上重大な影響がある一方で,会社としては告訴したというだけでは損害を回復できるわけではなく,横領分の金銭の支払いを求めても拒絶される可能性もありますし,報道により会社の信用が低下することもありえます。
そのため,慎重に判断すべきですが,悪質なケースで社会的な要請が大きいなど,告訴することで会社の社会的評価を保てるような場合には,告訴に踏み切ることも考えられます。
金銭の返還を優先させ,懲戒解雇としない代わりに横領金の返還を確実にさせる,という交渉をすることも考えられます。
たとえば,横領金の返済について保証人など担保を付けるとか,分割支払いを合意して公正証書にしておく,といった方法もあります。
この点は,あくまで懲戒処分とすることで秩序の回復を重視するのか,経済的な回復を重視するのかで変わってくるかと思います。
横領をした従業員に対する対応は,ケースによって様々です。
横領行為が判明して懲戒処分や賠償請求等が必要となった場合は,まずは弁護士に相談して,アドバイスを受けながら対応することが解決への近道だと思います。